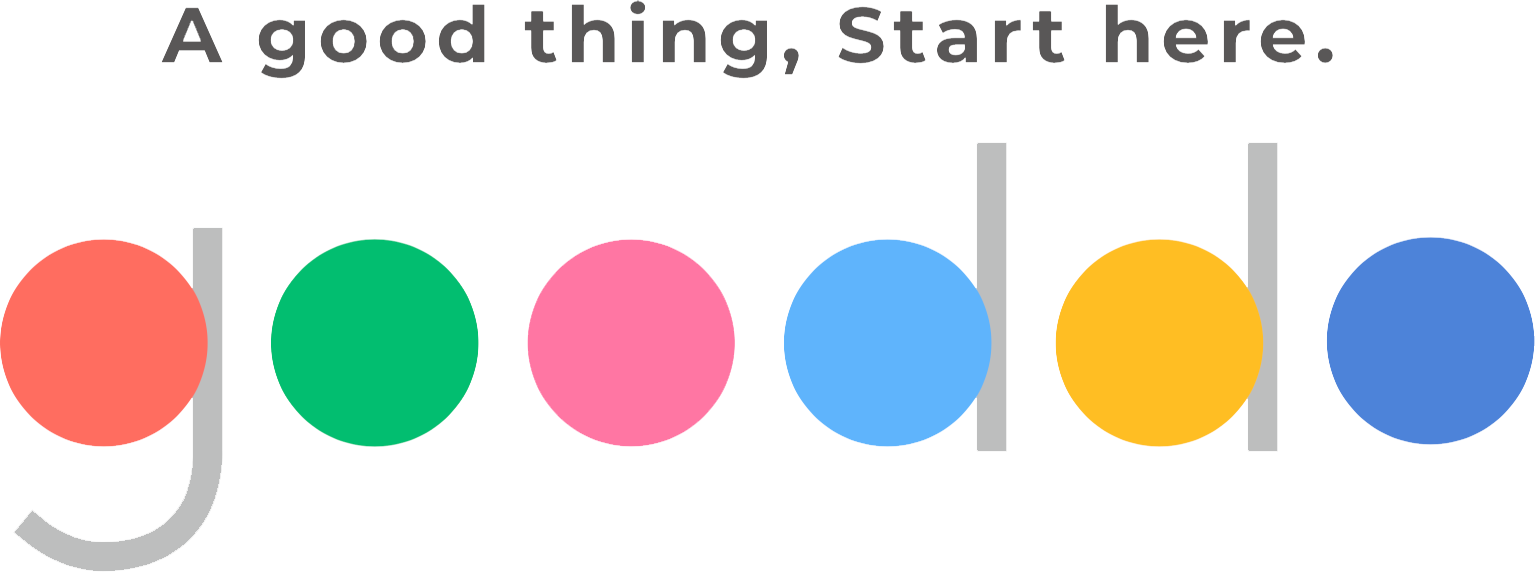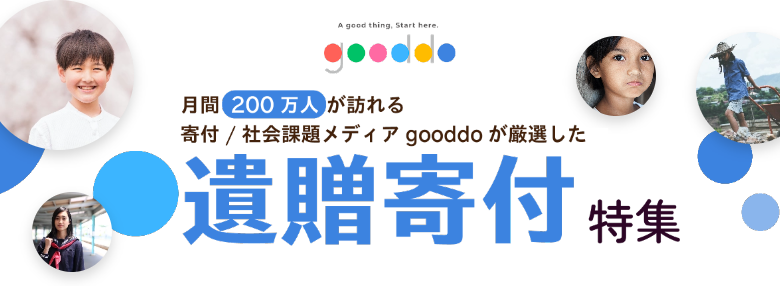
よくある質問
Q1遺言による遺贈寄付はどうやって手続きするのですか?
遺言による寄付の手続きは、以下の流れでおこないます。
①寄付先団体の担当者や弁護士などへ相談
②遺贈について記した遺言書を作成、保管
③ご逝去後に遺言書が開示
④遺言執行により指定団体等へ遺贈
注意したいのは、遺言書の作成方法です。遺言書が正しく作成および保管されないと、遺贈が無効になってしまう恐れがあります。
Q2相続財産から遺贈寄付すると寄附金控除を受けられますか?
相続財産からの寄付の場合でも寄附金控除を受けられます。
ただし、寄付先の団体が寄附金控除の対象団体である場合に限ります。また、控除を受けるには寄付した相続人の確定申告が必要です。
寄付先の団体が控除の対象かは各団体へ問い合わせをして、確認しましょう。
Q3遺贈寄付の相談窓口はどこにあるのでしょうか?
遺贈寄付の相談先は次のような窓口があります。
・遺贈寄付先の団体
・寄付先の紹介窓口
・市区町村役場 など
遺贈するか迷っている段階であっても、ほとんどの団体が相談を受け付けてくれます。弁護士も遺贈について詳しい専門家ですが、費用などを考慮すると相談のハードルが高いと感じる人もいるでしょう。
相談内容にもよりますが、まずは遺贈したい団体へ相談するのも一つの方法です。
Q4不動産を遺贈寄付できますか?
不動産も遺贈寄付することが可能です。しかし、不動産は管理や換価等にリスクがあるため、受け入れる団体が少ない可能性があります。
特に山林や農地、リゾートマンションの遺贈は困難です。不動産を遺贈できるかどうかは、必ず寄付先の団体へ事前に確認しておきましょう。
Q5不動産を遺贈寄付すると新たに税金が発生しますか?
不動産の遺贈では、遺贈を受けた団体や相続人に新たに税金が発生する可能性があります。特に意識しておきたい税金は次の3つです。
・登録免許税
・不動産取得税
・みなし譲渡課税
登録免許税や不動産取得税は、不動産を受け取った者にかかる税金です。登録免許税の税率は相続人の場合は1000分の4ですが、受遺者の場合は1000分の20になります。
また、相続人には原則として不動産取得税はかかりませんが、受遺者にはかかります。
みなし譲渡課税は、法定相続人に納税義務が生じます。ただし、みなし譲渡課税は必ずかかるものではなく、不動産や株式などに含み益がある場合のみ発生するものです。